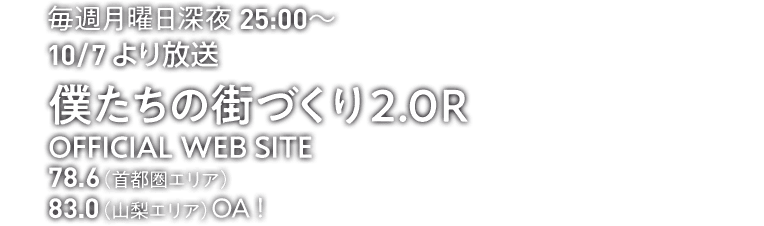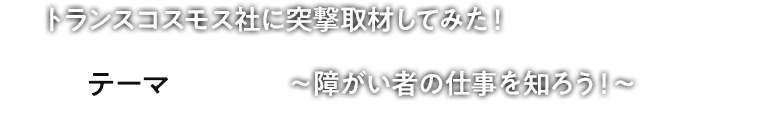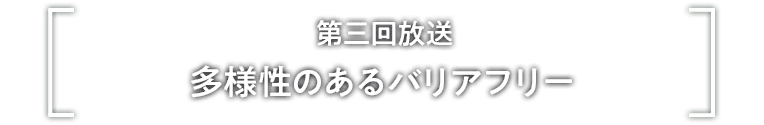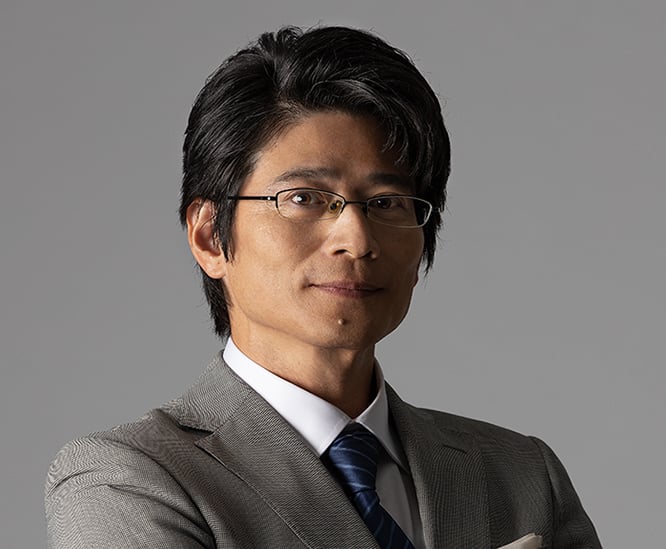多様性のあるバリアフリー(第三回放送)
音声はコチラ- 大串
-
今回はスタジオを飛び出し、400人以上の障がい者を雇用している東京・渋谷にあるトランスコスモス社に取材して「障がい者の仕事を知ろう」と題してお送りします。
- 徳田
-
そしてゲストには、障がい者の立場から幅広く芸能活動を続ける乙武洋匡さんをお迎えしています。
乙武さん、引き続きよろしくお願いいたします。
障がい者にとって出歩きやすい街とは?ロンドンと東京のバリアフリー環境の違い
- 徳田
-
先週もいろいろなお話を伺えたのですが、今週はより深く深く掘ってお話できたらなと思います。
ところで、乙武さんは趣味とかは何かあったりしますか?
- 乙武
-
長く10年以上ハマっている趣味としては、落語を聞きに行くことですかね。
ここ1~2年はそれに加えて歌舞伎を見に行ったり、友人にオペラを教えてもらっていたりと。
あとは、ワインかな?ここのところハマっていて、ついに自宅に小さなセラーを購入して、もっぱら家で飲んでいますね。
- 徳田
-
それは素敵ですね! ちなみに旅行とか旅とかもよくされるんですか?
- 乙武
-
そうですね。ついこの間も、東ヨーロッパを二週間旅して帰ってきたばかりです。
一昨年の2017年は、一年間をかけて37カ国の放浪の旅に出ておりました。
- 大串
-
放浪ですか!?
- 徳田
-
目的を決めずにふらっと行く感じですか?
- 乙武
-
そうですね、目的があったところもありますが、基本的にはあまり決めずに。
その前の年にリオパラリンピックを見に行くためにブラジルには行っていたので、南米以外は全て回ってきました。
- 徳田
-
そうなんですね。やはり感じるものもありますよね。
- 乙武
-
特に一年間の中で一番長く滞在していたのが、イギリスの首都ロンドンだったんです。
やはり三ヶ月もおりますと、観光や仕事で行くのとは違って人々の生活に触れるところがあるので、感じるところは一番大きかったです。
ロンドンはニューヨークと並ぶ世界二大都市と言われていますから、行く前のイメージとしてはバリアフリーも進んでいるのではないかという勝手なイメージでいたんです。
ところが実際に訪れてみるとそうでもなく。ロンドンは世界で最初に地下鉄が開通した街らしくて、エレベーターがついている駅というのは全体の四割くらいしかないようです。
それもまだいい方で、2012年のパラリンピックが開催される前まではもっと少なかったそうなんですね。
地下鉄に限らず、街中にはヴィクトリア朝時代の建物がごろごろしているので、なかなかバリアフリーが進んでいないというのが現状だったんです。ところが、不思議に思えたのが、ロンドンの街中を歩いていると……
これは大げさではなく、2~3ブロック歩いていると一人くらいのペースで、車椅子ユーザーの方を見かけるんですよ。
私は東京に住んでいますが、丸一日、朝に家を出て夜帰ってくるまでの間に車椅子ユーザーの方を見かけたとして一人。見かけないで終わる日もあるくらいの頻度ではないかなと思うんです。
東京にしてもロンドンにしても、人口における車椅子ユーザーの方の比率というのは、本来それほど変わらないと思うんですよ。
ではなぜロンドンでは頻繁に見かけて、東京ではあまり見かけることがないのか?
ロンドンに住んでいるうちにだんだんそのヒントが見えてきたんです。
- 徳田
-
やはりヒントがあるんですね。
- 乙武
-
先ほどもお話ししたように、地下鉄にはエレベーターがついてない駅が多くある。
ところが、車椅子ユーザーの方やベビーカーを押しているような親御さん、みなさんエレベーターがついていないはずの駅に向かうんですよ。
当然エレベーターがないので、階段の上で困りますよね?
困っていると1分も経たないうちに、にょきにょきと誰かの手が伸びてきて、誰かが運んでくれるんです。
みなさんそれをわかっているから、エレベーターというインフラがなくても、人の手助けというインフラがあるので気軽に外に出かける。なのでエレベーターがなくても地下鉄を利用するんですね。
- 大串
-
ハードではなくてソフト対応なんですね。
- 乙武
-
おっしゃる通りなんですよ。
それが今、日本だとどうなっているかといいますとどうせ誰かが手伝ってくれるだろうと前提に外に出かけると、"自分のことも自分でできないのに、誰かに手伝ってもらうことを織り込み済みで出かけるなんてとんでもない"という、「自己責任」という言葉がとても広がってしまっている。
そのためになかなか出かけられず、手助けが必要になったらどうしよう?ということで外出を躊躇されてしまう方も、まだまだ多くいらっしゃるようなんですよね。
そういった物理的なバリアフリーが整っていることはもちろん大事ですし、そういった意味ではロンドンよりも日本の方が軍配があがると思うんです。
でも、実際どちらの方が障がい者や車椅子ユーザーにとって暮らしやすい、出歩きやすい街なのかな?と考えると、もしかしたらロンドンの方が上という部分もあるのかもしれない、と感じましたね。

アフリカ・ルワンダでの実例から学ぶ誰もが暮らしやすい街づくりのヒント
- 大串
-
街で出会う確率を考えると、やっぱりロンドンの方が、障がい者の方も気軽に出かけられるのかもしれないですね。
- 乙武
-
そうですね。
やはり助け合うということにおいては、障がい者と健常者の関係性だけでなく、子育てについても同じことが言えると思います。
日本だと、たとえば電車などで子どもがぎゃあと騒ぐと、「なぜ公共の場に連れてくるのか」「なぜ公共機関を使うのか」なんて言われてしまいますよね。
ところが、私もびっくりしたというか反省させられたんですが、ロンドンでは小さい子どもが騒いでいても周りの大人はあまり注意をしないんです。
「なんであれ誰も注意しないの?」と聞いたら、「なんで注意するの?」と逆に聞かれてしまって。
「だって周りに迷惑じゃない」と続けたら「だって子どもってそういうものじゃない」と返されてしまいました。日本では、「公共空間では全ての人が静かにしているべきだ」という大人のルールに子どもを合わせようとしている。
ロンドンでは「子どもは騒ぐのが自然である、だから静かにできる大人は静かにすればいいし、子どもは自然なままでいればいい」という感覚をみなさんが共有しているんだなと思いました。実はロンドンだけでなく、いろいろな国や都市を回っていたのですが、アフリカのルワンダという国に行ったことがあったんです。
そこである日本人女性と知り合いまして、彼女はシングルマザーなんですが、ルワンダでタイ料理屋さんを経営されているんです。
二年前までは、みなさんの誰もが耳にしたことがあるような日本の一流企業で勤務をなさっていたそうです。
お給料も相当良かったと思うんですけれども、なぜそこをわざわざ退職してルワンダに移住をしてきたんですか?
そうお伺いしたら、「子育てのためです」とおっしゃるんです。ルワンダというと、数十年前に大虐殺があった国というイメージが根強く残っていることもあり、子育て環境は日本の方がいいのでは?と思ってしまいがちではないかなと思うんです。
でも彼女が言うには、教育と医療、この二つはさすがにルワンダよりも東京の方が圧倒的に良いです。
しかし職場に子どもを連れてきて良いかどうか、普段街中で子育てをしているときの周りの大人の対応、空気、人々の助け合い。そういったところまで考えると、東京よりルワンダの方が子育てしやすいと感じる、とおっしゃっていた。
それが悪い意味で印象的でした。そうか、子育て世代にとって、日本はそこまで子育てしにくい国だと感じられてしまっているんだなと思いました。子育て世代であったり、車椅子ユーザーであったり、誰かのちょっとした助けを必要としている方にとって、今の日本はどれだけ暮らしやすい国なのか?
そう考えると、まだまだ改善する余地がたくさんあるのではないかなと感じましたね。
- 徳田
-
そうなんですね……。
ちょっとだけ意外だったかなとも思って。
結構日本は、もっと寛容で、優しい部分があるんじゃないかと思っていたので。
おもてなし精神があったり、すぐに手を差し伸べるのかと思いきや……
やはりそういうことに出くわす回数が少ないからこそ、どうしていいかわからない戸惑いがあるんでしょうか。
- 乙武
-
そうですね、徳田さんのおっしゃる通り、日本人が不親切だから手伝ってくれないというわけではないと思います。
日本では長らく分離教育といって、障がいのある方とない方が別の環境で教育を受けるということが続いてきました。
ですのでどうしても健常者にとっては、慣れていないというところが大きいと思います。
いざ大人になって社会に出たときに障がい者の方と会っても、どう接したらいいんだろう?とか、どんなお手伝いをしてさしあげたらいいんだろう?なんて戸惑ってしまう。
もっと言うなら、下手に声をかけたら逆に失礼になってしまったらどうしよう、なんて気を遣ってしまう部分もあると思うんですよね。
ですから慣れていないという前提をしっかり踏まえた上で、お互いが触れ合う機会を増やしていった上で、自然な形で手助けをしてあげたり、頼むことができたり、そういった社会にしていけたらいいなと思いますね。
- 大串
-
日本の均一性というのが、逆に多様性を受け入れて優しくするということに不慣れな土壌になってしまっているのかもしれないですね。
- 乙武
-
本当にそうですね、やはり日本は第二次世界大戦で敗北を喫してから、驚異的なスピードで復興を遂げてきました。
その根本にあるのは合理性ですとか、効率性を重視したことにあります。
つまり働くのは健康な成人の男性である。そこに労働力を絞り込み、まさに均質性を武器に高度経済成長を果たすことができた。
その裏で、例えば女性であるとか、例えば障がい者であるとか、メインの労働力からは溢れる人たちのことは後回しにされたり、排除することでシステムが出来上がってきてしまった。
一時は世界第二位の経済大国になったわけですから、そのあたりから経済成長を最優先するのを止めて、これまで後回しにされてきた方々を社会に迎え入れていこうという動きが本来なら成されていかなければいけなかったのかなと。
とはいえ失った時間のことを考えても仕方がありませんから、トランスコスモス社さんのように素晴らしい一例もありますので、そういったことを見習っていただいて、大きな企業や組織で様々な方が働ける環境作りに力を入れていっていただきたいなと思いますね。

お互いの理解と尊重を深めて多様性のある社会の実現へ
- 徳田
-
乙武さんご自身としては、社会であったりこれまでの生活の中で、してほしいこと、してほしくないことってあるんでしょうか?
例えば、そこまではしてほしくないんだけどなとか、周りに対する要望だったりとかはありますか?
- 乙武
-
私の場合は基本的に電動車椅子であちこち出かけてしまうんですけれども、足がないということは電動車椅子である程度補完できても、棚の上のものを手に取るとか、そういったことができなかったりしますね。
なので買い物に行っているときに周りのお客様に「ちょっとあれ取っていただいていいですか?」なんてお願いすることはありますね。私も本を出してから21年間、よく聞かれる質問トップ3に入るものとして「障がい者の方とどう接したらいいですか?」というものがあります。
ただこれってとても難しい質問なんですね。
例えばお二人も、「健常者の方とどう接したらいいですか?」「女性とどう接したらいいですか?」なんて聞かれても、いや、それは人によるとしか言いようがないと思うんですよ。それと一緒で、障がい者と接するにはと聞かれても、それもやっぱり人によります。
私なんかはこういう性格ですから、ずけずけと物が言えてしまいますし、初対面の方にスーパーや本屋さんの中で頼みごとなんかも言えますけれど。
もちろん、なかなか内気で自ら頼めないような性格の方もいらっしゃると思います。
そういったことを考えると、周りの方が何かお手伝いが必要ですか?なんて声をかけてあげられたらいいのかなと思いますね。
- 大串
-
アメリカとかでは、知らない人でも「あれ自分に話しかけてるんだ!?」くらいの感じで声をかけてくれたりしますよね。
- 乙武
-
そうですね、たとえ、健常者の方であっても、みるからに東洋人という見た目で、なかなか英語が喋れないんじゃないかというように受け取られれば、「Can I Help You?」と声をかけてくださる機会ってすごく多いと思うので。
なんていうのかな……例えば、普通に生活していて、目の前の方がお財布を落としたらどうしますか?
小走りで駆け寄っていって、落としましたよ!って声を掛けると思うんです。
それって、どんなお手伝いをしてあげたらいいんだろう?傷つけてしまったらどうしよう、失礼にあたるんじゃないかとか考えないと思うんです。
そういったくらいの距離感で、障がいのある方の手助けもしていただけたらいいのかなと思っています。
- 徳田
-
人とのコミュニケーションのお話が出てまいりましたが、今の時代は空気が読めないとか自分のことを伝えられないことを、アスペルガー障害とかコミュ障とかいうこともありますよね。
そういったコミュニーケーションがうまく取れない方に対して、乙武さんからアドバイスはありますか?
- 乙武
-
そうですね、まずは、味方や理解者を一人ずつ増やしていくということかなと思います。
自分はこういった特性がある。多くの人はその言葉で通じることも、自分には伝わらないんです、ということを理解してもらえる人を少しずつ増やしていくしかないのかなと思います。
逆にそういった特性がない人に対しては、世の中にはそういった特性の人もいるんだよということを知っていただきたい。学校の教師をやっていて子ども達に「まっすぐ帰るように」といったら、普通は「どこにも寄り道せずに家に帰る」という意味だと思いますよね。
でも例えばアスペルガーの方だと真顔で「先生、学校から出るとすぐに突き当たりの交差点があるので、まっすぐ家には帰れないんです」と道がまっすぐという意味に捉えてしまったりするんですよ。
私たちの中では笑い話になってしまいそうなことでも、彼らの中では大真面目にそうとしか捉えられなかったりする。
理解力というものにも多くの特性があるということを、多くの人が理解してくれることが、裏を返せば彼らにとっての味方を増やしていくことに繋がるのかなと思いますね。
- 徳田
-
周りの理解も大事ですよね。
- 大串
-
最後にゲストの方に毎回お聞きしているのですが、未来の日本はどうなっていると思いますか?
またはどうなっていたらいいと思いますか?
- 乙武
-
昨年から法律が変わって、海外からの労働者が日本に増えてくるようになりましたね。
現実としては多様な社会になっていくのかなと思います。
ただその多様な社会というのが、摩擦がなく多様さが溶け合った世界になっていくのか?
それともその多様な人々が分断され、ときには衝突しながら共存していく世界になるのか。
そこは、これからの私たちの心の持ちよう、腕の見せ所なのかなと思いますね。
今のまま、何も対策を打たずに、努力をしないままであれば、後者のまだら模様の分断された世界になってしまうのかなという懸念は持っておいた方がいいと思います。
そうではない、違う特性があってもお互いに理解しあって尊重していける、そんな世界にしていきたいと私は思っています。
- 大串
-
多様性を受け入れるだけではなく、なおかつその人たちと一緒にやっていくんだという心構えを持っていかないといけないですね。
- 乙武
-
多様性を受け入れると口で言うのは簡単ですけれど、それを実現しようとすると自分たちも変わっていかなくてはならないところ、我慢しなければいけない部分は必ず出てくると思います。
でもそれを受け入れないと多様性のある社会は実現しないと心に留めて、私たちも前に進んでいかないといけないと思いますね。

- 大串
-
今回はスタジオを飛び出し、400人以上の障がい者を雇用している東京・渋谷にあるトランスコスモス社に取材して、ゲストには乙武洋匡さんをお迎えしてお送りいたしました。
乙武さん、ありがとうございました。
- 乙武
-
ありがとうございました!